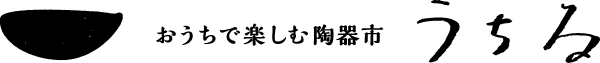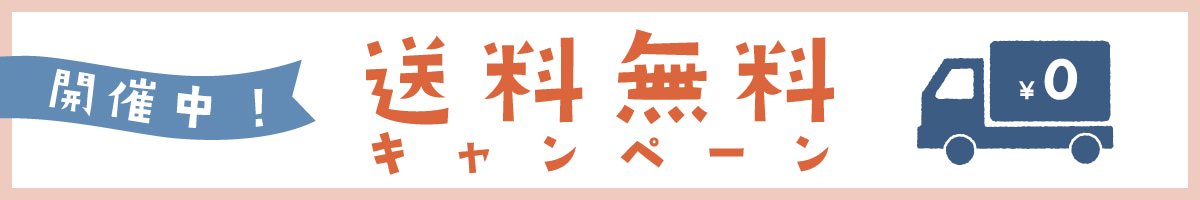酒器 お猪口(おちょこ)
| 1 - 15 / 全15商品 |
| 1 - 15 / 全15商品 |
新入荷
再入荷
開催中のイベント
もっと見る作風から選ぶ
-
 【ほっこりかわいい】思わずにっこりしちゃう、かわいいうつわがいっぱい。
【ほっこりかわいい】思わずにっこりしちゃう、かわいいうつわがいっぱい。 -
 【シンプル】シンプルながらも、凛として美しい作品に出会えます。
【シンプル】シンプルながらも、凛として美しい作品に出会えます。 -
 【土の温もり】土ものならではの素朴でいて力強い作風を感じられます。
【土の温もり】土ものならではの素朴でいて力強い作風を感じられます。 -
 【染付】伝統的な染付を現代の暮らしに寄り添ったかたちで。
【染付】伝統的な染付を現代の暮らしに寄り添ったかたちで。 -
 【民藝・民陶のうつわ】民藝ならではの素材や技法を感じられる作品を集めました。
【民藝・民陶のうつわ】民藝ならではの素材や技法を感じられる作品を集めました。 -
 【上品なうつわ】繊細な彫模様や装飾が、品のある佇まい。
【上品なうつわ】繊細な彫模様や装飾が、品のある佇まい。 -
 【木工・漆器】一つ一つ手仕事で仕上げた手間ひまのかかった作品ばかりです。
【木工・漆器】一つ一つ手仕事で仕上げた手間ひまのかかった作品ばかりです。 -
 【ガラス】透明感のあるものや、細工の凝ったものまで。
【ガラス】透明感のあるものや、細工の凝ったものまで。 -
 【キッチン用品】使い勝手の良いキッチン用品、厳選しました。
【キッチン用品】使い勝手の良いキッチン用品、厳選しました。 -
 【北欧食器】デザイン性と実用性を兼ね備えた、北欧生まれの食器。
【北欧食器】デザイン性と実用性を兼ね備えた、北欧生まれの食器。